ギャンギャンを出産してから約8ヶ月後、私は再び職場に復帰。仕事、2人兄弟育児、家事。と目まぐるしい毎日でした。
ギャンギャンはハイハイや歩き始めが、やや遅かったものの。1歳前には犬や猫を見て「ワンワン」「ニャンニャン」と指さして喋ったり、「ギャンギャンくーん」と呼べば「ハーイ!」と手をあげて返事をしてくれたり。そんな姿に、私は普通に安心して過ごしていました。
2歳半健診での衝撃
ところが、2歳半健診で「指さしをしませんね」と指摘を受けました。「え?え?前はしてたのに?」と驚きました。
そういえば最近、指さしだけでなくおしゃべりも減っているかも……。でも、私は「何かの間違いだろう」とその時はノンキに思っていました。
健診の担当者からは「一度、大きな病院で診てもらってください」と勧められました。幸い、大学病院で出産したギャンギャンは、3ヶ月に1回発育検診に通っていました。なのですぐ大学病院の発達の専門医に診てもらえました。
診断結果は「小児自閉症」
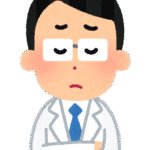
指差ししないなぁ。3歳になっても変わらなければ、診断しましょう
と言われて。祈る気持ちで迎えた3歳誕生日。相変わらず指差しもしないギャンギャン。「小児自閉症」と診断されました。
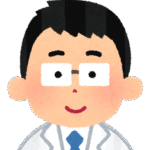
早くから支援を受けたほうが親は楽ですよ
と、主治医の勧めに従い。すぐに市役所で療育手帳の申請や、通所支援の申請を行い。療育に通いだしました。
「またなの?」と押し寄せるショックと不安
長男と三男を亡くしてきた私にとって、「自閉症」という言葉は新たな絶望のように響きました。「なんで?」「どうして?」「私はまともな子育てはできないの?」――そんな思いが頭の中をグルグルと渦巻いていました。
しかも、もう気軽に相談したり助けを求めたりできる母もいない。心のよりどころもなく、ただただ真っ暗闇の中にいるような感覚でした。
兄リーリーの療育と、ギャンギャンの違い
一方。兄のリーリーも、3歳くらいから療育に通っていました。保育所時代からとにかく落ち着きがなく、家でも常に動き回っていました。外食ではコップを倒したり、食器を落としたり……。外食は「ご飯を食べに行く」ではなく「怒りに行く」ようなものでした。
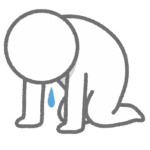
他の家族は食事を楽しんでるのにぃ〜〜〜〜!!!!
なんでウチは怒ってばっかりなの?????
「これはやっぱりなんだか普通じゃないのかも?」と思い、市役所に自ら相談に行きました。支援の面接では「支援が必要なレベルではないかもしれません」と言われましたが。私は納得できず、療育につなげてもらいました。
療育を通して、リーリーは多動だけでなく、言語化や想像力の弱さ、手先の不器用さ、模倣の苦手さなど、多くの特性が明らかになりました。
そして、このことはその後の療育で、リーリー自身。自分の特性を理解し、対処法を学べたことはとても大きな意味があったと今では思っています。
でもリーリーのときは、「将来の学習に困らないように」という前向きな気持ちがベースにありました。
しかしギャンギャンは違いました。
1歳のころは普通に発達していたからこそ。「得ていたものを失っていく」ショックも大きかったのだと思います。
保育所での言葉と支え
2歳からギャンギャンは市営の保育所に通っていました。小さなころは周囲との発達の差は少なかったものの、年齢が上がるにつれて差はどんどん広がっていきました。
私は市役所に加配の保育士の手配をお願いし、なんとか共働きを続けながらリーリーと2人を療育に通わせていました。
けれど、ある主任保育士から、こう言われてしまいました。
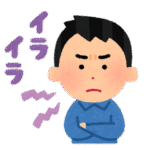
ギャンギャンくんに手がかかってしまって!他の子どもたちに迷惑だと思わないんですか?!
所長室に呼ばれて、「ココ(保育所)ではなく。専門の療育施設に通った方がいいのでは?」と、暗に“出て行け”と告げられたこともありました。
当時は、保育所から療育園に週2回。送迎サービスで10時〜15時に通わせている状態でした。
当時はそういったサービスを駆使。平日は朝7時半から夕方6時半まで、長時間保育をお願いして、なんとか仕事に通えていた状態でした。
なので、そういった施設は預かり時間が短く、通わせるということは。私が仕事を辞めなければなりませんでした。この時も月収の少ない我が家には、それを選ぶことはできなかったのです。
もちろん、土日祝祭日も仕事はあったので。そういった日は、放課後デイサービスの行う療育に通わせていました。
それでも、すべての保育士さんがそうだったわけではありません。
ギャンギャンが砂遊びが好きだと知った保育士さんは、わざわざ海の砂を取ってきてくれたり、「かわいいね」と笑顔で接してくれる保育士さんもたくさんいました。その存在に、私たちは本当に支えられました。
この時に、後々ギャンギャンの人生に1番役立っているボディーランゲージである「お願い」ポーズが身についたのです。本当に保育所での、読み聞かせタイムには感謝しかありません。

このポーズしたら、すぐ相手に伝わって便利!
ギャンギャンの体の丈夫さが、心の支えの1つでした
ギャンギャンの成長に、不安や葛藤がなかったわけではありません。「この子は一体これからどうなっていくんだろう?」と、何度も自問しました。
でも、その一方で、私はギャンギャンの体の丈夫さには安心していました。
長男のときは、ほんの少しの体調変化にも敏感になり、常に命への不安と隣り合わせでした。
ギャンギャンにはその“命に対する不安”がなかった。だから私は、どこかで「今すぐに死んでいなくなるわけじゃない。」と思えて前向きな気持ちでもいられたのだと思います。この手から、命がすり抜けてしまう不安がない安心感に支えられていました。
命の危機を乗り越えた出来事
そんなギャンギャン。 ある日の夜、我が家の2階の窓からコンクリートの庭に落下してしまいました。
この時夫は夜勤。私がお布団を敷いている間にリーリーと2人で遊んでいたほんの一瞬、目を離したスキのことでした。
助けようと外へ飛び出すと、ギャンギャンが自分で立ち上がり、私の元へ駆け寄ってきました。
この時すぐ救急車を呼びましたが、「自閉症」と伝えると受け入れ病院が(いわゆる受け入れ拒否) なかなか見つからず……。ドキドキしたのを覚えています。色々な病院に電話で要請をかけている消防士さんが諦めずに根気よく探してくださったことに感謝しています。
やっと受け入れの決まった夜間救急に運び込まれたギャンギャンは、喋ったり、指差などで自分の痛いところを伝える事ができないため。全身のレントゲンなどを撮ったりされました。
診断は前頭部の陥没骨折。けれど、それ以外はおそらく丸くなって落ちたおかげで他には大きな外傷もなく、奇跡的に命に別状はありませんでした。
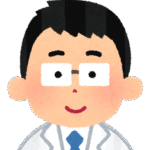
この子はすごい!本能的にちゃんと一番衝撃に耐えられるポーズを取ったに違いない!でないと、こんなに無事では済みませんでしたよ?!
救急医や救急スタッフさんたちが、「普通は命を失ったりするような大事故でしたよ。これは奇跡ですよ!」と驚いてました。
その後も、ギャンギャンはICUに私が付き添い3日間入院しましたが、。特に後遺症もなく無事退院出来ました。
それは良かったのですが。この間はリーリーの方が大変でした。自分が遊んであげていた弟が、目の前で窓から飛び出して落下してしまい。救急車に乗ってしまった。しかも一緒に母親もいなくなった。(同居の実父。つまりお祖父ちゃんはいました)事に大いにショックを受けてしまい。
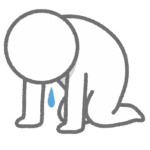
お兄ちゃんなのに〜!守ってやれなかったよ〜!
としばらくの間は、よく泣き出してしまっていました。優しい兄の葛藤を経験した出来事でした。
リーリー。小学校は支援学級に通い出す!
最近、小学校入学前は保育所でも「ひらがな」の学習時間を設けてくれていますよね。でも見事に覚えられないリーリー。「コリャこのままだとダメだよね・・」と通っていた療育の言語聴覚士さんと相談の末。リーリーは、地域の小学校の支援学級に入ることになりました。
支援級(特別支援学級)ってなあに??
支援級とは?
支援級(特別支援学級)とは、通常の学級(いわゆる「普通級」)とは別に、
発達障害・知的障害・身体障害・病弱など、さまざまな特性をもつ子どもが
より適した支援を受けながら学ぶことができる公立学校内の特別な学級のことです。
特別支援学校とは違い、同じ校舎内にある普通級との交流や行事への参加も可能で、
子どもの状態に応じて、支援級と普通級を行き来しながら学ぶ「交流学習」や「部分統合」も行われています。
支援級の対象となる子ども
支援級には、以下のような分類があります:
- 知的障害学級(知的支援)
- 自閉症・情緒障害学級(情緒支援)
- 言語障害学級(言語支援)
- 病弱・身体虚弱学級
- 難聴学級
- 肢体不自由学級 など
入級は、教育委員会や学校との面談・審査を経て決定されます。
療育手帳がなくても、支援級の対象になるケースもあります。(リーリーはこれです)
支援級と普通級の違い
| 項目 | 支援級 | 普通級 |
|---|---|---|
| 学級人数 | 少人数(概ね8人以下) | 約30〜40人 |
| 支援内容 | 個別指導・ペース調整あり | 学年一律の進度 |
| 教師 | 特別支援教育に理解ある教員 | 教科専門の教員 |
| 教材 | 状況に応じて工夫・調整可 | 教科書中心 |
支援級を選ぶ理由・メリット
- 子どものペースに合わせた学習ができる
- 感覚過敏・パニックなどにも柔軟に対応できる環境
- 少人数の中で自信や安心感を育てられる
- 必要に応じて普通級との交流も可能
注意点・親として考えること
- 地域によって支援体制・内容に差がある(コレは本当に大きいです!ウチの地域はたまたまラッキーなことに、とても良かったです)
- 将来的な進学・就労ルートにも影響するため、早めの情報収集が大切
- 子どもに合った学びの場を選ぶには、見学・面談・就学相談が重要
まとめ
「うちの子、普通級で大丈夫かな?」「支援級ってどうなんだろう?」と不安になる親御さんは少なくありません。
でも、子どもの“学ぶ権利”を保障する手段のひとつが「支援級」です。
無理に周りに合わせるよりも、その子に合った方法で学べる環境こそが大切です。
この時、思いもしない事が起こりました。リーリーを通わせる予定の「学童保育」のスタッフが言いました。
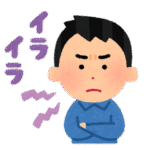
支援級に通うような子は受け入れません!他の子の迷惑ですから!
そんな事になったら、私が仕事を辞めなきゃならなくなってしまう!というか、納得できん!と思った私。
この時、すぐに小学校の支援学級のサポーターに相談しました!
幸いな事にリーリーの通う小学校は、支援教育に力を入れている学校でした。入学前から、支援級サポーターがついてくれていたのでその方に相談できたのです。「(学童保育)支援員が差別的な言動を!」とその方が猛抗議して下さった事と。幸いリーリーが他の子達のジャマになるような言動を取らなかったので。その後は無事に3年間学童に通うことができました!
リーリー。支援級に3年間在籍。結果は正解!
支援級では、ほぼマンツーマンの学習指導をリーリーに行って頂けたおかげで。(イヤ、これがほんとーに凄かったです。個人レベルに合わせた学習計画を柔軟に行ってくださいました)ほぼ遅れなく、4年生からは普通学級に進級することができました。きっと一般学級では、学習は大幅に遅れが生じていただろうなぁ・・・。と思っています。
この頃の私は、ただただガムシャラに生きていました!
リーリーとギャンギャンを育てながら、フルタイム共働き。同居していた実父は昭和の親父。育児や家事に協力的ではありませんでした。実母も亡く、周りに頼れる人も皆無でした。
そしてご存知のとおり、介護職は安月給のため何よりも常にお金が無い。仕事を辞めたらたちまち生活出来ない。なので仕事も辞められない状態の自転車操業。
毎週のように、私自身高熱を出しながら。朝は5時起きし、帰宅は19時。家事に追われながら0時に就寝。身体の丈夫でない私にはキツかった。
休日は、リーリーやギャンギャンの療育に通っていました。とにかく毎日が激戦・激闘でした。
今回も、最後までお読みいただきありがとうございました。
次回:とうとうやってきた!ギャンギャンの小学校進学!ココに分厚ーい壁が登場です。我が家がどうやって乗り越えたか?をお伝えします。


コメント